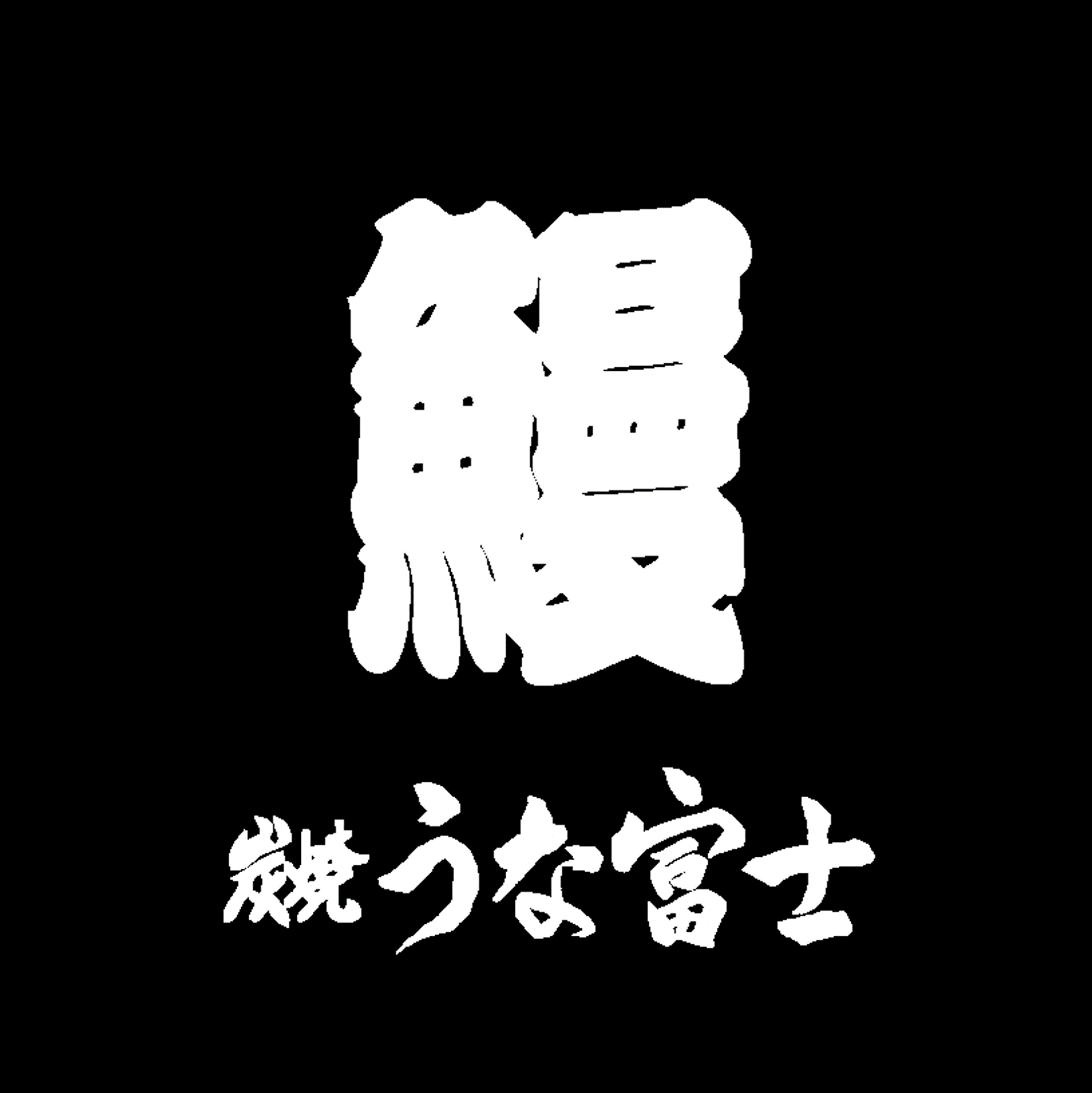【公式】炭焼うな富士
名古屋の名店「炭焼 うな富士」
うなぎが旨いこと
朗らかで明るいこと
永く続くこと
創業25年でミシュラン掲載
"ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版"
"ビブグルマン"受賞
食べログ選出
”THE TABELOG AWORD" 4年連続
”百名店”3期連続選出
一般的な店舗のサイズからすると3割以上大きい
こだわりの青うなぎを使用し、
当店自慢の上うなぎ丼や上ひつまぶしなどで
ご提供いたします。
1000度を超える紅蓮の炎で熱した後、
炭火でじっくりと身に火を通したうなぎは、
表面はパリパリ、中はふわふわでジューシー。
うな富士の本物の「うなぎ」をご堪能ください。
うな富士について
~名古屋の人気うなぎ店~ 創業100年以上の老舗うなぎ屋が多いなか、わずか25年でミシュラン掲載や食べログ百名店での選出など、数多くのうなぎ店が軒を連ねる愛知県という”うなぎ激戦区”で常に高い評価を得ている「うな富士」・・・・・・ もっと見る
店舗情報

【公式】炭焼うな富士
- 住所
- アクセス
- 営業時間
- 定休日
- 決済方法
- 現金: 可
- クレジットカード ; VISA マスター アメックス DINERS JCB
- 備考